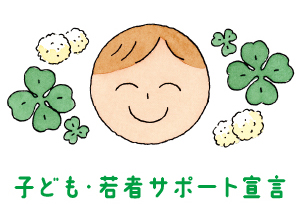2025年1月24日(金)に「ヤングケアラー支援の今とこれからを考える」オンライン公開ミーティング(主催:日本財団 後援:こども家庭庁)が開催され、こども家庭庁・自治体・民間団体のそれぞれの立場からの報告およびディスカッションが行われました(詳細なプログラムはこちら) 。
当日のリポートをお届けします。
※この記事は後編です。前編はこちらの記事をご覧ください。
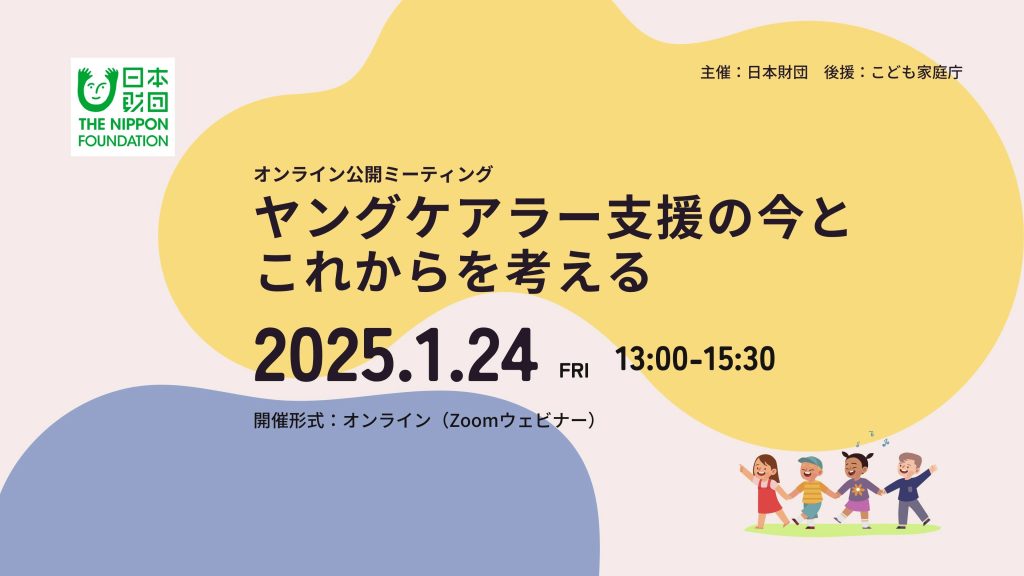
公開ディスカッション
公開ディスカッションでは、鈴木秀洋氏がモデレーターを務め、先の登壇者である長井氏・石岡氏に加え、こども家庭庁支援局虐待防止課課長補佐の古藤雄一氏、ケアラーワークスのピアサポートスタッフ友田智佳恵氏がパネリストとして登壇し、ヤングケアラー支援に関する取り組みや課題について、さまざまな視点から活発な議論が交わされました。



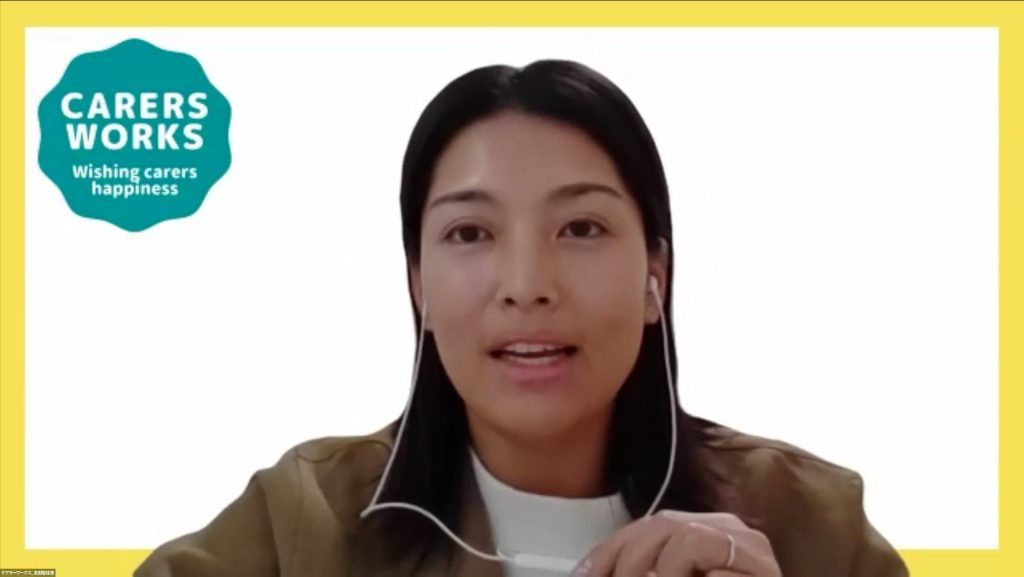
1. 当事者の視点から見たヤングケアラー支援の課題
鈴木氏:ケアラーワークスの友田さん、自己紹介と印象に残った話をお聞かせください。
ケアラーワークス 友田氏:私は12歳の時に母がくも膜下出血で倒れてから、身体障害と脳障害のケアを、今日まで 20 年以上続けている当事者です。本日の実践報告をお聞きして、全国に取り組みが広まっていると感じましたが、ヤングケアラーの気持ち、まなざし、ご家族の歩んできた道のりに対する配慮などへの理解がより深まるとよいのではと感じました。
2. 個人情報の取り扱いと支援の枠組み-制度の課題と対応策
鈴木氏:続いてこども家庭庁の古藤さんに自治体から個人情報や守秘義務の問題。18歳までというような枠組みの要保護児童対策地域協議会でその範囲を拡大していく、子ども・若者支援地域協議会の引き継ぎというところが課題かと思いますが、現状の法的整理についてお聞かせください。
こども家庭庁 古藤氏:改正法の施行に伴い、発出した施行通知の中にも個人情報について記載しています。端的に言うと「要保護児童対策地域協議会(要対協)」と「子ども・若者支援地域協議会(子若協)」の連携が重要なのですが、この連携に関しては、個人情報の関係で、現行法では整理されていないというのが実情です。しかし、運用上どうクリアしていくかについては、「要対協」と「子若協」のメンバーがお互いの協議会のメンバ ーとして入り、その中で情報共有する工夫などを自治体に申し上げております。また、重層的支援体制という枠組みを活用することで、個人情報の課題を乗り越えていくことも考えらえます。
施行にあたっての説明会等でも個人情報に関する質問を多くいただいています。こども家庭庁で Q&A も掲載していますが、体系立てて分かりやすい情報発信を検討しています。
3. 県のバックアップと市町村との連携
鈴木氏:滋賀県の長井さん、県のバックアップということで、積極的に豊富なメニュー作りや支援について発表していただきました。バックアップの重要性や市との役割分担に関して「うちの県では難しい」という他県の声も聞きます。工夫があればお願いします。
滋賀県 長井氏:市町から相談があった場合は、いったん話を聞いて一緒に考えていく姿勢を大切にしています。滋賀県ではコーディネーターを配置し、現場の方の支援の事例や状況を話しやすい状況にしています。また、市町、地域を超えて広域で支援を行う民間団体に補助を行っています。課題解決が難しい場合であっても民間団体を巻き込みながら一緒に考えていくこともできる。また話を聞き共有することを大切にして、その中で県としてできることがないか考えています。
4. 切れ目のない支援体制の構築-市町村の視点から
鈴木氏:葛城市の石岡さん、支援は市町村が中心になるかと思いますが、先ほどから教育、保健、福祉、様々な部局との調整が難しいという声があります。切れ目ない支援体制作りについてお伺いできますか。
葛城市 石岡氏:部局が分かれていると情報共有が難しいですが、現在は福祉と教育が連携して一体的に運用しています。もし障害福祉サービスが必要なケースがあれば、社会福祉課の障害福祉部門に声かけすることで、一緒にサービス運営を考えていくことがスムーズになります。つなぎっぱなしではなく一緒に運営していく。市が中心になり司令塔として、支援がどうなっているか把握し進めていくことを心がけています。
鈴木氏:司令塔がどこかというのは重要ですので参考になります。続いてパネリスト間のクロストークとなります。それではまず長井さんからお願いできますか。
5. 国が市町村に期待する役割と支援の方向性
滋賀県 長井氏:こども家庭庁にお聞きします。支援の問題であったりとか体制面の問題であったりとか、なかなかコーチングすることが難しい地域もあります。国から、市町村含めてで、県なども実施してほしいこと、期待されているようなこと、お聞きできればと思います。
こども家庭庁 古藤氏:今回の法制化を踏まえ、ヤングケアラー支援体制を全国に浸透、構築していきたいと思います。皆様のお話にもありましたが、ヤングケアラーに気づくということがとても大事です。気がつかないことには支援を届けられませんので「子どもと家庭に気づきましょう」ということです。そのための実態把握に向け、それぞれの市町村において実態調査をお願いしたいと考えています。全ての市町村で実態把握に取り組み、支援対象の子どもと家庭に気づき、必要な支援が何かを考えながら、支援体制の構築等に進んでいただければありがたいです。
6. 子どもが安心して自分の状況を話せるために
ケアラーワークス 友田氏:実際の支援で子どもやそのご家族と接している葛城市さんにお聞きします。ヤングケアラーの子どもたちが声を上げることが重要だと思いますが、子どもたちが声を上げやすい、自分の状況を打ち明けやすい工夫はありますか。18 歳の子どもとの繋がりも発表がありましたが、実際にその方はどのようなきっかけで葛城市との繋がりができていたのか教えてください。
葛城市 石岡氏:子どもの声を聞くことを重要視して日々支援しています。学校では相談システムを通じて自分の声を届ける、近くの大人に相談することが大事なのだと、教職員の皆さんも認識した上で対応しています。実際、高校を卒業して地域に出て18歳以降となると、この状況がいつまで続くのかと将来的な不安も多い中で疲弊し、就職断念や引きこもりになるという相談も受けています。そこで一緒に就職に再挑戦する取り組みをしています。一緒にハローワーク行く、自己肯定感が下がっていたら、それをリカバリーする働きかけをしながら、当事者の声を聞いて、一緒に少しずつ歩みながら、将来社会に出られるよう、家庭の状況も踏まえながら支援してもらっています。
18 歳以降はこども・若者地域支援協議会になりますので、支援にあたっては、他の関係機 関や支援団体に状況を伝え了解を得た上で、本人の同意のもと連携に進んでいきます。
鈴木氏:ありがとうございます。最後に皆様からご感想やご提言があればお願いします。
7. 感想など
こども家庭庁 古藤氏:ヤングケアラーの支援は社会全体で取り組んでいく必要があり、子どもと家庭を守っていこうという意識が広がることは社会が一つ成長したということだと感じます。社会の中で仕組みとしてきちんと当事者を守れるように落とし込んで、地方自治体の方、民間の皆さんと、広報や啓発も含めてがんばっていきたいと思います。
滋賀県 長井氏:当事者の方からは「話を聞いてもらう」「ご飯を一緒に食べる」だけでも支えになったというお声もいただきます。日々の声がけや見守りも非常に重要な支援の視点だと思います。そのような視点で皆が温かくヤングケアラーを包括できるように手を取り合っていければと考えています。
葛城市 石岡氏: 今日のお話で、県や民間の立場がよくわかりました。今後もそれを活かしながら連携を進めていきたいと感じました。
ケアラーワークス 友田氏:実践報告の中で私の心に残っているところは、滋賀県の発表の中で、地域の中で多様な経験を積めるように体験活動を大切にしているということです。ケアを担う状況にある子どもたちがライフチャンスを逃さないような社会になってほしいと思いますし、その子どもたちがケアを担うか担わないかということは選べることです。仮に担うという選択をしたとしても、自分らしく家族も大切にしながら幸せに暮らしていけるような社会になっていくように私も尽力していきます。
質疑応答
Q1:こども家庭庁に対して、1 つ目、ヤングケアラー支援に関する今後の国の予算計画についての質問が来ています。
また、2つ目の質問は、支援者の方からで、「包括的な関わりを持つ支援活動では、短期的な効果を示すことや成果の数値化が難しく、それが行政などでの予算確保に影響する可能性があります。また、短期的な成果を求められる中での支援者の焦りやストレスは支援の質にも影響しかねません。こうしたヤングケアラー支援の上での評価、支援の成果、短期的な成果という部分についてどうお考えでしょうか」というものです。
こども家庭庁 古藤氏:まず、予算の話についてですが、令和6年6月に法律を改正してケア支援を法制化しました。今年度はこれに関連した補正予算を組んでおり、主な内容としては、実態把握に取り組んでいただく際のイニシャルコストを補助するメニューを設定しています。併せて18歳以上の当事者への支援として、都道府県の方に18歳以上の当事者の支援を担うコーディネーターの配置経費という形で補正予算を組んでおります。さらに、令和7年度においては、広報啓発等についても、一歩進んだ正しい理解を社会に発信する予算も確保していく予定です。
ご質問の2点目、支援実績について、我々が思っているのは、救われた家庭とか子どもがどれだけいるかという数より、つながった数そのものが大事だと思っています。結果の部分の数では評価しないことが大事なのではないか、と。子どもとつながれる場あるいは機会がどれだけ確保できたか。数で評価するとしても、そういった観点で評価するということが必要ではないかと考えています。
Q2:えひめ権利擁護センター新居浜 山本さんへ質問です。「つなぐシート」作成の際に参考とした資料があれば教えてください。また、活用状況や課題について教えてください。
えひめ権利擁護センター新居浜 山本氏:「つなぐシート」の参考にした資料はたくさんあります。不登校や虐待などの子どもに関係するチェックシートはもちろん、多様なチェ ックシートを統合しながらブラッシュアップしていきました。最初から完璧なものができ
たのではなく、今使っているものはバージョン7です。名称も最初は「チェックシート」としていましたが、「チェックシート」という名称だと先生方に心理的な抵抗感があったようで「つなぐシート」に変えました。常に見直しをしながら、より現場に即したものに改良してきました。
つなぐシートは以前より広まりましたが、まだ定着しているとは言い難いです。つなぐシ ートによってスクールソーシャルワーカーにつながり、その後、子どものサポートが充実していくことを理解してもらうところまで学校の先生方に十分伝えきれていません。先生方もご多忙ですので、教育委員会や不登校コーディネーターの先生方から現場の先生に伝えていただいています。私たちも学校訪問をして、その際につなぐシートの説明をし、「気になる子どもがいたらつなぐシートで情報提供してください」と働きかけています。(※編集者注:つなぐシートについては、自治体モデル事業に関する初回調査報告書においても紹介しております。詳細はこちら:https://youngcarer.jp/modelproject/)
Q3:スクート 内海さんへの質問です。「まつなぎや」でヤングケアラーだと気づいた後の支援対応について教えてください。
スクート 内海氏:大村市のこども家庭課と、2週間に1度、利用している子どもたちに関して情報を共有する機会を作っています。そこで家庭に対する行政支援へつなげます。既に行政が支援している家庭でも、例えば、支援計画の見直しなどをしていただくという形で連携してその後の支援につなげています。また、支援が必ずしも必要ではない場合というのもありますが、その際もまつなぎやで見守りを続けるという形をとっています。
クロージング~同じ立ち位置での“ミーティング”

鈴木氏:本日は学会報告や行政説明ではなく、あくまで“ミーティング”として、同じ立ち位置での話し合いができました。
こども家庭庁による法改正のご説明から、今後の補助のあり方について強い意志を感じました。自治体としては、この補助をうまく活用して、人的体制やサービス拡充を図っていくことが求められます。
県の立ち位置としては、規模や人口の異なる市町村に対してどのようにバックアップしていくか、マニュアル作成や広報啓発の重要性が強調されました。滋賀県は県でありながらオーダーメイドで対応し、二者関係にならないように配慮している点が、今後の広域バックアップの参考なります。
市の立ち位置では、ヤングケアラー支援の中心となる「司令塔」の重要性が挙げられました。切れ目のない支援を実現するためには制度設計や具体的な取り組みが不可欠であり、ワンストップサービスや相談の工夫についても大いに学びました。
民間の取り組みについても貴重な意見がありました。ケアラーワークス(府中市)からはヤングケアラーの悩みに寄り添う支援が大切であること、家族全体を支援するネ ットワーク会議の重要性が示されました。えひめ権利擁護センター新居浜(新居浜市)からは、スクールソーシャルワーカーや「つなぐシート」の活用、関係機関の間での役割分担が共通認識として大切であることを学びました。スクート(大村市)の内海さんからの「共にいる時間が大事で、ショートカットはできない」という言葉は強く心に残りました。
本日の報告内容が全国に発信されることが、ヤングケアラー支援に取り組む他の自治体や地域の後押しになると確信しています。参加いただいた皆様におかれましては、本日共有した資料やアイデアを持ち帰り、実践に活かしていただきたいと思います。